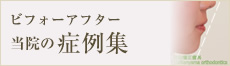舌側矯正を始める方へ

これから裏側からの矯正治療を始める方、今すでに治療中の方。
きれいな歯並びは健康な歯があってこそ、です。
特に舌側矯正・舌側矯正を選ぶ場合は、他人から見えにくい治療ため、自分でも見えづらいということですから、表側からの治療よりもさらに予防に気をつける必要があります。
歯ブラシ、フッ素ジェル、デンタルフロス、歯間ブラシなどで常にクリーンな歯を心がけたいものです。
歯ブラシ

矯正装置の周囲には、どうしても汚れがたまりやすくなってしまいます。
矯正治療中においては、専用の歯ブラシが存在します。装置のまわりを掃除しやすいように“山型”“谷型”に設計されているのが特徴です。

また、通常の歯ブラシ以外に、裏側の矯正装置の間などの置細かい部分へのアプローチを容易にする“特別”な歯ブラシがあります。(プラウト)
フッ素ジェル
 日常の生活で無理なく使用が続けられるフッ素ジェル。
日常の生活で無理なく使用が続けられるフッ素ジェル。
矯正治療中などの虫歯リスクの高い方に最適なセルフケア用フッ化物製剤です。
様々な味があるので、お好みを選んでみてはいかがでしょうか。
デンタルフロス
 舌側矯正で虫歯のリスクを下げるには、歯ブラシだけでは不十分な場合があります。
舌側矯正で虫歯のリスクを下げるには、歯ブラシだけでは不十分な場合があります。
歯が接触している部分にはフロスを使用することをお勧めします。フロスは歯面に押しつけるように使用することで歯面の汚れを落とします。最近のフロスでは、唾液を吸うことでスポンジ状にふくらみ汚れをさらに落としやすくなっているものもあります。
歯間ブラシ
 歯間ブラシはデンタルフロスと同じく、歯ブラシでは取れない歯と歯の間の歯垢を取る器具です。
歯間ブラシはデンタルフロスと同じく、歯ブラシでは取れない歯と歯の間の歯垢を取る器具です。
針金に細かい毛がついた構造で、歯の間を掃除します。
歯垢染め出し液
 歯垢は乳白色で、歯ブラシで落とせているかどうかがとても見分けづらいものです。
歯垢は乳白色で、歯ブラシで落とせているかどうかがとても見分けづらいものです。
染め出し液により残った歯垢に色をつけることで、ブラッシングが確実になり虫歯を防ぐことができます。
キシリトール(xylitol)
 キシリトールはシラカバやカシから得られるキシランに水素を加えて還元してつくられる糖アルコールの一種です。
キシリトールはシラカバやカシから得られるキシランに水素を加えて還元してつくられる糖アルコールの一種です。
糖アルコールの中で最も甘い砂糖(ショ糖)と同じ糖度で、カロリーは3.0kcal/g(砂糖は4.0kcal/g)です。
またお口の中で溶ける際に吸熱反応(砂糖の8倍)が起こるので独特の清涼感・冷涼感が得られるのも一つの特徴です。
キシリトールの虫歯予防効果(静菌作用)
砂糖(ショ糖)の場合、ミュータンス菌(mutans streptococci:いわゆる虫歯菌)が糖を分解・発酵して酸をつくりだします。
その酸(pH5.7以下)によって歯のエナメル質が溶かされて虫歯ができてしまいます。
一方、キシリトールはミュータンス菌体内に取り込まれると、キシリトール5リン酸となるもののミュータンス菌はそれを代謝することができないために菌体内蓄積し、増殖を抑制することが報告されています。
すなわちキシリトールの場合は、ミュータンス菌によって発酵せず、虫歯のもととなる酸が発生しないのです。
*“キシリトール入りのガムを長期間食べ続けるとミュータンス菌の数が減る”
との報告がありますが、これはキシリトールの静菌作用というよりは、
“キシリトールを代替甘味料として用いた場合には、唾液あるいはプラーク(歯垢)のpHを下げないため、プラーク(歯垢)中で耐酸性の強いミュータンス菌より他の口腔内常在菌が優位になり、細菌叢が変化するためではないかと考えられています。
つまりキシリートールが抗生物質のようにミュータンス菌に直接作用して死滅させているとは考えにくいようです。
キシリトールの再石灰化作用
歯の表面のエナメル質を構成するハイドロキシアパタイトの結晶から、カルシウムなどのミネラル成分が溶け出して結晶構造が崩れる現象を脱灰といいます。
一度脱灰がおきても中性環境では唾液中のリン酸やカルシウムがそこに沈着して結晶のミネラル成分が回復します。この現象を再石灰化と呼びます。
私たちの歯の表面ではこの「脱灰→再石灰化」がバランスよく行われています。
しかし飲食回数の増加等、酸の発生する量と回数が増えると、再石灰化が追いつかずに脱灰が進行して“むし歯”を生じます。
キシリトールを含むガムを噛むと再石灰化が促進されるとの報告があります。
しかし、これはキシリトールの再石灰化作用というより、ガムを咬むことにより唾液分泌が促進されてその緩衝能によりプラーク(歯垢)のpHが上昇して、再石灰化が促進されたのではないかとも考えられています。
診療カレンダー
■:休診日です。